『蒲田前奏曲』
オフィシャル・インタビュー
2020-09-22 更新
松林うらら(企画・プロデューサー・出演)
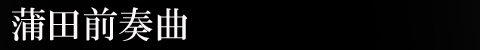

© 2020 Kamata Prelude Film Partners
配給:和エンタテインメント、MOTION GALLERY STUDIO
![]()
松林うらら
1993年生まれ、東京都大田区出身、映画好きの両親の影響で幼少期から映画の世界に魅了される。
18歳でスカウトされモデルとして活動を開始、2012年、『1+1=11』(矢崎仁司監督)で主役に抜擢され映画デビュー。
その後、映画中心に活動し、2017年には『飢えたライオン』(緒方貴臣監督)に主演、東京国際映画祭でワールドプレミアされ、その後、ロッテルダム映画祭など数多くの映画祭で絶賛され、プチョン国際ファンタスティック映画祭では最優秀アジア映画賞にあたるNetpac賞を受賞。
最新作は山戸結希企画プロデュース『21世紀の女の子』の中の山中瑶子監督作品「回転てん子とドリーム母ちゃん」で北浦 愛、南 果歩などと共演。
本作『蒲田前奏曲』が初プロデュース作。第15回大阪アジアン映画祭では『蒲田前奏曲』がクロージング作品として上映され、コンペティション部門国際審査委員として選出される。

![]()
売れない女優マチ子の眼差しを通して、“女”であること、“女優”であることで、女性が人格をうまく使い分けることが求められる社会への皮肉を、周囲の人々との交わりを介在しながら描いていく映画『蒲田前奏曲』。映画の公開を前に、本作プロデュース・出演の松林うららのオフィシャルインタビューが解禁となった。
本作制作の経緯をお教えください。
3年前の主演作『飢えたライオン』では海外の映画祭に訪れる機会が多くあり、日本だけでなく世界に目が向くようになりました。海外の方と接する中で、映画に対する視点が180度変わりました。女優として、ただ待っているだけではなく、何か人とは違う行動に移したいと常日頃から感じるようになりました。自分で企画して映画を創りたいと本格的に思い始めたのは、『21世紀の女の子』のコプロデューサーで、後に本作のエグゼクティブ・プロデューサーとなる小野(光輔)さんにご相談したところ、絶対に作ったほうがいいよと言われてからです。女優として活動していく中で、今回のテーマになっているようなハラスメントについてや自分の環境の中での葛藤があったので、そういうことを含めて作品にして昇華できたらなと思いました。例えば、女優って華やかな職業に見えて、実は地味な仕事で、普通に働いている女の子のほうが目立っていたりいい服を着ていたりします。女優であっても、必ずしも環境によっては主人公になれない、中心になれない。女優としての自分の現状の立場からも考えました。
どうせなら監督は自分でやりたいとも思ったんですけれど、ちょうど東京国際映画祭で穐山(茉由)さんの『月極オトコトモダチ』という映画を観た時に、「この方に女子会編の監督をお願いしたい」と思いました。安川(有果)さんは、監督された『21世紀の女の子』の一編『ミューズ』が私も好きな作品だったので、ハラスメントについては安川さんにお願いしたいと思いました。栃木県大田原市で作品を撮り続けている大田原愚豚舎の渡辺(紘文)さんもずっとファンで、東京国際映画祭の時に「東京中心主義の批判」というテーマで、この間のウディネ・ファーイースト映画祭で上映された新作『わたしは元気』にも主演している、大田原在住の(久次)璃子ちゃんをキャスティングして、いつもの渡辺節で政治的な要素をラップのように話して下さいとお願いしました。中川(龍太郎)さんは、『Plastic Love Story プラスチック・ラブ・ストーリー』という映画が昔から好きで、仲良くさせていただいていて、中川さんの詩的な部分をぜひ本作のオープニングとして撮っていただけないかなと思っていました。私には弟がいるのですが、中川さんには、弟に彼女ができた際に嫉妬したこと、いわゆる「ブラコン」をテーマに何かできないかとご相談しました。
「連作にするというスタイルを選んだ理由は?
大阪アジアン映画祭が、インスピレーションの源です。というのも、2019年に観たフィリピン映画『視床下部すべてで、好き』に、とても感銘を受けたのです。ヒロインのアイリーンを演じたイアナ・ベルナルデスさんは、第15回大阪アジアン映画祭コンペディション部門出品作『女と銃』(ラエ・レッド監督)のプロデューサーでもあります。この話が興味深いのは、アイリーンはヒロインだけど、主人公ではなく、彼女に妄想を抱く4人の男たちの群像劇である点です。日本にはこのタイプの群像劇はあまりないので、4人の監督にお願いし、最初は撮る監督によってマチ子の見え方が違うという主観的な話でしたが、もっと膨らませて、今の形になりました。蒲田の街もそうですし、各パートごとにいろいろな主人公が含まれている映画です。穐山さんのパートだと、伊藤沙莉さん演じる帆奈が主軸で闘う女性がメインになっていきます。
蒲田で4人の監督でやるのだったら、新しい「連作長編」という形でできないかということで話を進めました。最初は、女性は環境によって顔や態度を変えていかないと生きづらいというテーマを元に、“一人の女優が環境によって違った顔に見える”という構想から始まりました。監督たちとお話をしていく中で、次第にそれぞれのパートごとのテーマが見えてきました。最終的にマチ子という主軸が全ての話に通じているという形になり、マチ子のまわりのそれぞれの環境の中で立ち向かう強き女性が出てくるということで物語が繋がっています。4人の監督は、脚本のすり合わせだとか全くしていないんです。それぞれに、お願いしたいテーマと、マチ子のキャラクターの説明と、蒲田を使って欲しいというお題だけ出しました。
最終的な作品の順番は、中川さん、穐山さん、安川さん、渡辺さんという順番になりましたが、監督4人の作品の並び順はいつどのように考えたのですか?
当初は、渡辺さんの作品が女性監督の作品に挟まれるという構成で10分ずつモノクロの渡辺さんの作品が入るという案もあったのですが、最終的にはそれぞれの監督の作家性を活かす形となりました。
渡辺さんには蒲田の町を見ていただき、蒲田を撮ることも考えていらっしゃった時期もあったんですけれど、やっぱり大田原出身で大田原映画の監督なので、そこはぶれなかったです。劇中では触れられていませんが、マチ子自身が大田原出身という設定にしました。最初はマチ子が大田原に行くという予定ではいたんですけれど、撮影時期がずれたりして、実現しませんでした。他の3編は夏に撮り、渡辺さんだけ11月に撮りました。
中川さんの作品は、脚本を読んだ時点で、「これはオープニングだろうな」と想定していました。撮影は、穐山さん、安川さん、中川さんの順番で撮りました。渡辺さんを一番最後に持ってくることで、3作品を批判しているんじゃないかと捉える方もいらっしゃるんですけれど、私としては回収として一番しっくりきました。また、出来上がってみて時間軸がそれぞれに違ったことに気づきました。中川さんは「大過去」、穐山さんは「現在」、安川さんは「過去、トラウマ」、渡辺さんは「未来」というサブテーマがあり、渡辺さんの作品では子どもの未来であり、マチ子に投げかけるりこちゃんで作品は終わります。過去から未来へ、中川編の歴史観念からの脱却、穐山編の現在の私たちのステレオタイプ、安川編の微妙な性と、常に問題になる女性への無理解、渡辺編はエピソード0であり、そこから私が今回プロデュースに至った映画を撮るということに無意識的に接続されてゆく構成として繋がっていると思っています。反逆のための前奏曲と接続する話だと思っています。
深作欣二監督の『蒲田行進曲』に何か関係はあるんですか?
内容は全く関連していないです。『蒲田行進曲』はすごく好きな作品だけれど、新しい作品にしないといけないということで、本作は連作映画になっています。『蒲田行進曲』は階段落ちが有名なんですけれど、本作ではないです(笑)。『蒲田前奏曲』というタイトルが決まってから、曲のように第一、第二、第三、第四と続くようにと思って、それぞれを「第一番」「第二番」などと呼び始めました。
マチ子役を自分で演じるというのは最初から決まっていたんですか?
はい。マチ子は主軸でありながらも、極力目立たないようにしたかったです。伊藤(沙莉)さんなり瀧内(公美)さんなりが”強き女性”として目立っているので、それはよかったと思います。

第1番ですが、空襲が触れられますが、蒲田ということで監督から出てきた発想なのでしょうか?
私はそこは全く考えていなかったんですが、撮影は終戦記念日が終わった直後だったのもあり、戦争と繋げた中川さんはさすがと思いました。うまく蒲田の今と昔を繋いでいただきました。
第2番は、5人の女子会から始まりますが、キャリア志向の女性と、とにかく結婚したいという女性と意見が分かれるというのも実際にある話で、実はどちらも嫉妬しているところがあると思うのですが、監督とはどのような話をされましたか?
私も穐山さんも“結婚”というワードに敏感というか、「なんでそんなに結婚に焦るんだろう」という会話から始まったので、それが活かされたのだと思います。穐山さんにお聞きしたら、登場人物の全員に自分の一部が入っているとおっしゃっていました。
第3番ですが、男性監督が意識が高いような映画の企画をしておきながら、実は自分が過去にセクハラ・パワハラをしていたというのもありえる話ですし、言っていることとやっていることが違うというのは、映画監督やセクハラ問題にかかわらず、世の中あふれていることですが、監督から出たアイデアなのでしょうか?
私の実体験を安川さんにお話ししたのがきっかけです。ある作品で、プロデューサーにセクハラをされたことがあったのですが、周りの人は見て見ぬふりだったし、セクハラに反対だと言っている監督の関係者にもセクハラをする人がいたりだとか、粋がっている方こそ本当はどうなのというのは安川さんと話していました。私としては、自分の体験を昇華させるために安川さんの作家性を活かして作って欲しいと伝えました。
第4番は、渡辺監督が女の子に話しかけるという構成は、どのような経緯で決まったんですか?
いつも渡辺さんの作品は、一方的に渡辺さんが喋り、主演の方は車を運転し喋らないのです。渡辺さんがずっと社会への不満を一方的にしゃべるという作風が多くて、私は『プールサイドマン』という作品が好きなんですけれど、そのようなイメージで、「渡辺さんはずっと喋ってください」とお願いしました。渡辺さんのこの作品は結構深いテーマを意味すると思います。渡辺さん演じる監督は、世間のことを批判的に喋り倒すんですけれど、女の子たちはシンプルな言葉でしりとりをしていて、「大人ってうるさい」「純粋な気持ちを取り戻して欲しい」というテーマもあるんではないかなと私なりに解釈しています。
それぞれの作品の面白い撮影エピソードをお教えください。
第1番は、一番最後の道のシーンのために、朝の3時に蒲田に集まって、4時くらいから撮影を始めました。
第2番の撮影は本当に女子会という感じでした。伊藤さんと福田麻由子さんは私の1歳下なんですが、ドラマ「女王の教室」(2005)で共演されていたのを私も小学校の時に見ていました。伊藤さんは現場を盛り上げてくださる方で、その時の話だとかをされていました。この2人の再共演を見たいという方が結構いるのではないかと思います。
第3番の繰り返しオーディションするところは基本アドリブです。大西さんにかなりアドリブを出していただいて、笑いが絶えなかったです。本当のオーディションみたいな不思議な感覚の撮影でした。
第4番の撮影は、スケジュールの都合で行けませんでした。
web媒体のインタビューの読者の方にメッセージをお願いいたします。
4編全然違う作風なので、最後まで楽しんでいただければと思います。
すごい社会派という映画ではなく、ユーモアも交えているので、滑稽で笑えてくるところも結構あり、大阪アジアン映画祭でも全てのパートに笑いが起きるくらいだったので、構えないで観ていただきたいです。日常的に無意識に生きている中でしていることや気づかない部分があると思うんですけれど、日常の中でこういうことが起きているということを感じていただいて、自分の現実と重ねて考えていただけるきっかけになったらいいなと思います。
(オフィシャル素材提供)
![]()
関連記事
・舞台挨拶付き特別先行上映
・初日舞台挨拶



