『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
第72回カンヌ映画祭 公式記者会見
2019-05-25 更新
レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピット、マーゴット・ロビー、クエンティン・タランティーノ監督
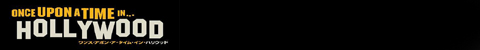
 配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント8月30日(金) 全国ロードショー
![]()
先日現地時間5月14日に開幕した、第72回カンヌ映画祭のコンペティション部門に正式出品されている、クエンティン・タランティーノの9作目の長編監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。大盛況の公式上映を終え一夜明けた5月22日(水)に、タランティーノ、レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピット、マーゴット・ロビーらが公式記者会見に出席。大勢の記者の前で今までベールに包まれていた本作のストーリーについて語った。タランティーノが「今までの作品の総括のような部分も無意識的に出ていた」と、過去8作品の集大成であると語る本作について、レオナルド・ディカプリオは「監督にしてみたら原点回帰なのかな。幸運にも僕らが仕事をさせてもらってるこの業界に対するラブレターなんだと思う」とコメント。また、ブラッド・ピットは「レオは人物が崩壊する瞬間を、今まで見たことがないくらいの素晴らしい演技でそれを表現してみせた」と、ディカプリオの演技を絶賛し、マーゴット・ロビーは、自身が演じたシャロン・テートという役が「物語の心臓」であると表現し、「私の目から見て彼女は一筋の光だった」と明かした。
【公式記者会見Q&A】
9作目となる本作について。
クエンティン・タランティーノ監督: 自分の作品をそこまで意識していたわけではないけれど、結果として今までの作品の総括のような部分も無意識的に出ていたと思う。脚本を最初に読んだうちの一人が助監督のビル・クラークなんだけど、彼は『ジャッキー・ブラウン』以降ずっと僕の助監督を務めてきて、『パルプ・フィクション』でもパーソナル・アシスタントだった人物だ。彼無しで映画を作ることは想像ができない。その彼が脚本を読むために僕の自宅に来て……、なぜなら脚本は外に出さないから僕の家に来ないと読めないんだ。それはここにいる皆んなもよく知っていることさ。それでビルがうちに来た時に、「これが9作目か。どんなものか?」と言ってプールサイドに行って脚本を読んで、読み終えて帰ってくると、「おいおい、9作目は今までの8作が合わさったような感じじゃないか」って言ったんだ。そういうふうに考えたとこはなかったけど、確かにところどころそういった部分はあるかもしれない。

(フランチェスカ役の)ロレンツァ・イッツォについて。
クエンティン・タランティーノ監督: ロレンツァとは友達だし、僕の友人のイーライ・ロスとも何回か一緒に仕事した作品も見ているから、彼女がどんな女優かは知っていた(※ロレンツァはイーライの妻でチリ出身)。違う役柄を演じた主演作も3作品くらい見ている。だからといって単に彼女に役を挙げたわけではない。彼女はオーディションを受けに来たんだ。すごいのは、イタリア語の台詞を覚えただけでなく、イタリア語でのフレーズを20個ほど覚えてきてたんだ 。警察に話を聞かれてるあの場面も、あれは彼女のアドリブなんだ。アドリブができるくらいイタリア語を習得してたんだ。とても驚かされたよ。それに彼女は映画の中でとても面白いキャラになってると思う。正にあの時代のイタリアン・コメディによく出てくるうようなおっちょこちょいな若手女優を見てるようで完璧だった。
マンソン・ファミリーについて。
クエンティン・タランティーノ監督: これだけ我々が興味をもってしまうのは、どこまでいっても、底が知れないからだと思う。僕もかなり調べものをしたし、学術的ではないにしろ、多くの人も(この何年間の間に)本の1冊や2冊を読んだり、(話題にもなった)ポッドキャストを聞いたり、数年に一回くらいやるテレビでの特番などを見ていると思うんだ。彼があの少女たち、少年もだけど、どのようにして自分のコントロール下におけたのかが本当に理解を超えてる。しかも知れば知るほど、情報を集めれば集めるほど、具体的になるにつれ、何も解明されていかない。むしろ余計に不可思議になってくるんだ。解らないからこそ、本当の意味で理解するのが不可能だからこそ、僕らは引き込まれると思うんだ。
役柄について。
レオナルド・ディカプリオ: 今回の役はいろいろな意味で自分と重なる部分があるとすぐに思った。僕もこの業界で育ったからね。時代が変わる中、この人物はどこかその外にいて、取り残されているんだ。だからこの映画は僕にとって、今の自分がいられる立場に対して強い感謝の気持ちを改めてもたせてくれた。リックという人物は急に自分の苦しみと闘うことになる。自信を保つことや、仕事を繋ぐことに必死なんだ。僕は業界人の友人が多いから彼の気持ちが分かるし、こういう機会をもらってどれだけ自分が恵まれているかも分かっているから、それに対しては感謝の気持ちしかない。

監督について。
レオナルド・ディカプリオ: クエンティンの独特な作業の進め方について答えるならば、映画史だけでなく、音楽やテレビを含めこれだけの総合的な知識を持った人物は世界でも数少ないと思う。まるでコンピューターのデータベースにアクセスしているみたいだ。その知識の泉は計り知れないし、どんどん湧き出てくる。この映画はある意味、自分たちのいるこの業界に対するラブ・ストーリーを描いてるんだと思う。そしてその作品の主役に2人の異端者を置いた。60年代がやってきて、業界に置いてけぼりを食らった二人を。このテーブルに座っている全員も一時は業界の異端者だと感じたことがあると思うけれど、この映画は監督の業界に対するラブレターでもあるし、敬愛する人たちへの感謝を表したものなんだと思う。僕らはラルフ・ミーカー、エディ・バーンズ、タイ・ハーデンなどの作品を勉強してきた。監督の中で、芸術的な観点でその仕事ぶりを尊敬し、映画やテレビの世界に多大なる貢献をしてきた人物たちだ。僕にとってもそういった部分がいろいろな意味で一番感動した。監督にしてみたら原点回帰なのかな。他にどう言っていいのか分からないけど、幸運にも僕らが仕事をさせてもらってるこの業界に対するラブレターなんだと思う。

作中の人物たちについて。
ブラッド・ピット: 監督が作り上げたリックとクリフという二人は、一人の人物にも思える。最終的には“受け入れる”ということなんだ。自分の立場や人生への受け入れ、周りや環境、壁や悩みを受け入れること。リックという人物は時々笑えてしまうくらいそれらに振り回され、物足りなさを感じ、人生は自分に対して厳しいと思っている。そしてここにいる仲間のレオは、人物が崩壊する瞬間を今まで見たことがないくらいの素晴らしい演技で表現してみせた。一方クリフという人物は、その段階を通り越し、自分の身の程を受け入れ、平然とした心持ちで、来るものを拒まず、なるようになると分かっているんだ。だから僕にとってこの映画は「受け入れる」ということがテーマなんだ。
映画の時代背景に関して。
ブラッド・ピット: あの時代、マンソン事件が起こった1969年は、それまでフリーラブのムーブメントがあったり、希望に満ち溢れ、新しいアイデアがどんどん出て来てて、シネマも新しく変わろうとしていた時代だ。そしてあの出来事が起き、シャロンや他の人の悲劇的な犠牲があった。なぜ人々が恐怖を覚え、今でも取り上げられるかというと、人間の闇の部分を見つめることとなる暗く悲しい極めて重要な出来事だからで、何か純粋さが失われた瞬間だった。そしてこの映画はそれを素晴らしい形で表している。
役作りについて。
マーゴット・ロビー: 調べものもいっぱいしたし、見られるものや読めるものは全て参考にしたわ。でも同時に、役者の仕事は自分の役がストーリーの中でどのような役割を果たしているのかを理解するのが大事なんだと思う。だからより重要なのは、なぜこの人物が物語の中に存在しているか、なの。早い段階で監督は私に言ったわ。「彼女は物語の心臓(あるいは鼓動)だ」と。私の目から見て彼女は一筋の光だった。だから私は光でありたいと思った。それが私の仕事であり物語に対する役割であると思った。それを表現することが、多くの人がこの世界においてまぶしい光のような存在だったと語る、本物のシャロン・テートの追悼にもなると思った。

本作に取り組むにあたって。
マーゴット・ロビー: 他の役とのやり取りなどを通して自分の役の理解を深めることが多いけれど、今回のように自分自身で役に向き合う時間をこれほどもらったのはあまりないことだった。役者としてそれはとても興味深い経験だった。それをさせてもらったことに感謝しているし、表現したかったものが表現できたと思うからよかったわ。


(オフィシャル素材提供)
![]()
関連記事
・画像初解禁!
・第72回カンヌ映画祭ワールドプレミア
・LAプレミア
・来日記者会見
・ジャパンプレミア レッドカーペットイベント




