『マクベス』オフィシャル・インタビュー
2016-04-21 更新
ジャスティン・カーゼル監督
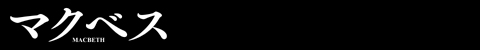

© STUDIOCANAL S.A / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 2015
![]()
ジャスティン・カーゼル監督
1974年、オーストラリア・ゴーラー生まれ。
ヴィクトリアン・カレッジ・オブ・ジ・アーツの卒業制作として手がけた短編『Blue Tongue』(05・未)が、カンヌ国際映画祭やニューヨーク映画祭など13以上の国際映画祭で上映され、メルボルン国際映画祭で最優秀短編映画賞を受賞した。
その後、CMやミュージック・ビデオの監督を務め、『スノータウン』(11・未)で長編デビュー。オーストラリアのアデレード郊外で実際に起こった猟奇事件に基づき、連続殺人に加担していく少年の姿を描いた同作品は15以上の国際映画祭で上映され、カンヌの国際批評家週間・特別賞やオーストラリア映画協会賞6部門を受賞するなど、世界的な注目を集めた。また『スノータウン』を手がける前は、オーストラリアを代表する舞台デザイナーとして知られていた。
すでにクランクアップしている次回作は人気ゲームの映画化で、再びマイケル・ファスベンダー、マリオン・コティヤールと組む歴史アドベンチャー『Assassin's Creed』。
![]()
ウィリアム・シェイクスピア没後400年にあたる2016年、人類史上最も偉大な作家の最高傑作「マクベス」が、荘厳なスペクタクルとエモーションをみなぎらせてスクリーンに甦る! 映画『マクベス』に挑んだオーストラリア出身の気鋭監督ジャスティン・カーゼルのインタビューが届いた。
『スノータウン』から『マクベス』までの道のりはどのようなものでしたか? マイケルと先に話しましたが、マイケルがあなたの参加を導いたように感じました。
『スノータウン』のあと、多くの異なるプロジェクトに取り組んでいた。特にその1本には、おそらく18ヵ月くらい費やしていたと思うが、実現しなかった。最終段階でダメになったんだ。そういうことがあったから、製作のイアン・カニングが僕にアプローチしてきた時、突然で驚いたんだ。
 マイケルとは、彼が『スノータウン』を観たすぐあとに会った。二人で何かしたいと思ったよ。僕は彼の大ファンだったからね。これは突然降って湧いた話だった。イアン・カニングが『マクベス』の脚色台本があると言い、僕はすぐに『分かった!』と答えたんだ。僕は舞台デザイナーだったから、『マクベス』の舞台を以前デザインしたこともあって、芝居のことはよく知っていた。でも自分の2作目の映画でシェイクスピアを監督するなんて思っても見なかったよ。マイケルがマクベスを演じると聞いた時、突然、それが説得力をもった。そのキャスティングと彼が演じることで、僕の頭の中に真っ直ぐにトーンとビジョンが飛び込んできた。そこから自然に事が運び、とんとん拍子で実現したんだ。
マイケルとは、彼が『スノータウン』を観たすぐあとに会った。二人で何かしたいと思ったよ。僕は彼の大ファンだったからね。これは突然降って湧いた話だった。イアン・カニングが『マクベス』の脚色台本があると言い、僕はすぐに『分かった!』と答えたんだ。僕は舞台デザイナーだったから、『マクベス』の舞台を以前デザインしたこともあって、芝居のことはよく知っていた。でも自分の2作目の映画でシェイクスピアを監督するなんて思っても見なかったよ。マイケルがマクベスを演じると聞いた時、突然、それが説得力をもった。そのキャスティングと彼が演じることで、僕の頭の中に真っ直ぐにトーンとビジョンが飛び込んできた。そこから自然に事が運び、とんとん拍子で実現したんだ。
考える時間を取りましたか? あるいは即決でしたか?
即決だよ。「これをやらなくては」と思った。
その時点で脚本はありましたか?
脚本は読んだよ。とても面白かった。まるで西部劇を読んでいるようだった。風景とスコットランドに大きな影響を受けていた。映画の初めのシーンで、キャラクターたちにはもろさが感じられる。彼らはボロボロになっている。僕は、マクベスが兵士の視点と立場で書かれていると感じた。さらに、この夫婦が子供を亡くしたこと、悲嘆に暮れていることが分かる。このキャラクターたちには何か途轍もない絶望が感じられる。この素晴らしい脚本は野心と予言による行動を活用し、キャラクターの人生における喪失感や生き残る方法を描いている。権力や強欲とは対照的に、この夫婦はともに絶望的な関係を続けていく。僕はそこに魅了されたんだ。
マクベスは心理的ダメージを受けた男ですか?
この夫婦の精神状態は不安定だと思った。そして二人はバラバラになっていた。マクベスは戦争に行き、何年もマクベス夫人とは会っていない。本当に厳しい状況だ。家族のいる人間たちに囲まれていながら、二人には家族がいない。それが彼らを追い込んでいるんだ。僕はそこに興味をもった。それがとても人間的に、現代的に感じられたんだ。そこから導かれていき、それが最初に、映画のビジョンとキャラクターの心理を見つける手助けとなった。
異なる解釈をもち、そこに新しい息吹を吹き込む人々がいることが、シェイクスピア作品が長く続いてきた理由の一つだと思いますか?
そう思うよ。それに作品に柔軟性があるからだと思う。解釈に対して門戸が広く、だからこそ魅力的なのだと思う。人々は何度もシェイクスピアを観に行く。それは常に異なる物語になるからだ。それが、シェイクスピアが成功した理由だと思う。面白いことに、この映画を編集しながら、僕はTVシリーズ「ブレイキング・バッド」(08~13)をかなり観ていたんだ。
意図的にですか? あるいは夢中になったから?
夢中になったからだよ。それまで観たことがなくて、はまってしまった。同時に映画の編集もやっていたんだ。どれほどあのウォルターの人生がマクベスの人生に重なっているか。あの自動車事故、あのキャラクターの運命が向かうところ。彼らにはそれをどうすることもできない。まるでマクベスのようだと思った。それに彼らが意図的に自分を壊してしまうところが、人の心を引き付ける。それに、暴力と邪悪と暗闇にも興味をそそられる。僕は、彼が暴力によって解放され、暗い森の中に入り込み、戻れる道を見つけられるのに、それを手放すところが面白いと思った。
彼が暴力と切り離せないのは、戦闘のせいでしょうか?
そうだね。彼にとってダンカンを殺すのは簡単だ。いつもやっていることだし、自分が知っていることだからね。
学校で初めてシェイクスピアと出会ったのですか?
そうだよ。彼の戯曲を読んだけれど、あまりつながりは感じなかったな(笑)。
学校で真価が分かるのは難しい作品ですよね?
とても難しいと思ったよ。この悲劇はいつもカリキュラムに組み込まれている。その美しさとパワーに、ずいぶんあとになって気づいた。素晴らしい舞台作品をいくつか観るまで気づかなかった。とても奥深い、真実を感じた。突然、言葉が息づいたんだ。「分かったぞ」といわんばかりにね。韻を踏むセリフに導かれているようには感じなかった。感情が頂点にあり、言葉がそこから流れ出してくる。それを僕は決して忘れないだろう。突然、シェイクスピアの作品にまったく新しい認識をもった瞬間だったんだ。
初めて観たシェイクスピア劇を覚えていますか?
覚えているよ。ベルボア・ストリート・シアターで上演された「ハムレット」だった。オーストラリアの偉大な演出家ニール・アームフィールドが演出し、リチャード・ロクスバーグが出演していた。僕は14歳だった。最高の経験だ。
『マクベス』の脚本に関して、セリフへのアプローチはどのようなものでしたか? 神聖なものとして扱いましたか?
 いや、ごく自然だった。最もシンプルな方法を試そうとした。そしてストーリー・テリングも最もシンプルな方法で考えようとした。その中で出来事を明快に描き出す。たとえば、舞台上のキャラクターたちが言葉を通して表現するものをどうやって映画的に見せることができるのか? 言葉がない場面ではどうか? 映像で命を吹き込むことができるのか? それはダンスと同じだ。
いや、ごく自然だった。最もシンプルな方法を試そうとした。そしてストーリー・テリングも最もシンプルな方法で考えようとした。その中で出来事を明快に描き出す。たとえば、舞台上のキャラクターたちが言葉を通して表現するものをどうやって映画的に見せることができるのか? 言葉がない場面ではどうか? 映像で命を吹き込むことができるのか? それはダンスと同じだ。
我々が脚色台本を書いていた時だけでなく、撮影中も、特に編集中もそうだった。その多くで奥深く、本当に本能的な雰囲気をたたえる場面と時間にしたいと思った。素晴らしい西部劇のように風景が支配する世界。それと同時に親密な感情も表現したい。素晴らしいのは、カメラをそこに置くと、そこには詩だけが存在し、その言葉をカメラが静かに見守ることだった。それが真っ直ぐに、地に足がついていながら新鮮で親密な感情を作り出した。風景が大きな役割を果たしてくれたんだ。
セリフを自然に感じてもらうためにどのようなことをしましたか?
セリフの多くは事実を伝える。キャラクターの間の会話のほとんどはその瞬間を表現している。マクベスとバンクォーの海辺でのシーンがある。彼は去りながら「今晩夕食に来るか?」と言う。「ああ、戻ってくるよ」と彼は言う。それはまるで『グッドフェローズ』(90)のワンシーンのようだ。「俺が君を殺すつもりで別れを告げたことを君は知っている。でも本当はそんなことはしたくないんだ」とでも言うようにね。とても親近感のある、現代的な感じがするシーンだ。そして独白へと移る。それは宇宙や神々に話しかけるマクベスではなく、いつも身近な誰かに関連付けたことを言っているんだ。もう一度言うが、それは何かに親しみを見出そうとするとても人間的なことなんだ。
「マクベス」の公演にかかわったとおっしゃいましたが、それはどこですか?
アデレードだった。僕は美術をデザインした。演劇界にいた頃だ。南オーストラリア・シアター・カンパニーだった。18歳か19歳の頃だよ。
マイケルはすでに決まっていましたが、どのようにしてこのマクベス夫人を配役したのですか? 大満足の配役に違いありません。
信じられなかったよ。マイケルと僕でマクベス夫人の興味深い性質について話し合っていた。僕たちは彼女に対する“邪悪な魔女”的なアングルは避けようと思っていた。この映画では、悲嘆について、母親であること、そして家族について話し合った。どうやってこのキャラクターに共感を見出すか。特にこの映画では、彼女は唐突に現れる。舞台でも、突然彼女は「ではこうしましょう」と始める。では、彼女の歴史をどう形成するのか、夫婦の新密度はどれくらいなのか、それが要となる。二人にはこの映画が始まる前から生活がある。そう感じさせることが大事だ。
マリオンの素晴らしいところは、人間性にある。彼女に共感し、マクベス夫人に大きな興味を抱く。俳優としての精密度、そして異国情緒に溢れた雰囲気、謎めいたところが、彼女を囲む、この非常に男っぽく力強い世界と対比され、素晴らしいコントラストになると思った。彼女の最後のシーンはかなりヒステリックな状態になるが、マリオンならスクリーンに見事な尊厳を表現してくれると僕は思った。彼女なら、このキャラクターにとても新鮮な感覚をもたらしてくれると思ったんだ。それに、彼女はただひたすら素晴らしい(笑)。
マイケルはこれほど難しい役を演じきり、あなたの期待に応えましたか?
信じられないくらいだ。二人ともね。僕にとって演技とは、「アクション」と「カット」の間に起こることだ。でも同時に、何かに耳を傾け、かかわり、打ち込むための、可能性が開くことでもある。彼ら二人は、準備を整え、どう仕事をするかについて一切の迷いがない。彼らの素晴らしい理解力を見て、驚きを禁じ得なかった。まるで一流のジャズを聴いているようだったよ。本能的で、自然で、本当にエキサイティングだった。特にこれまで何度となく発せられてきた言葉だ。彼らは心を開き、そのセリフに新鮮味を加えていったんだ。
風景が素晴らしいですが、イングランドでも撮影しましたか?
我々はノーサンバーランドにも行き、スカイ島でもたくさん撮影した。オーストラリアの大地も同じだ。僕がオーストラリアで刺激を受けたのは、『美しき冒険旅行』『荒野の千鳥足』(共に71)やピーター・ウィアー監督の『誓い』(81)といった壮大な景色を描いた映画だった。オーストラリアの景色は本当に雄大だが、そこから得る感情はとても奇妙なものだ。ものすごい威圧感がある。僕はスコットランドに行った時、同じものを感じた。自分がとても小さく感じるんだ。僕たちは、衣装にしても、出陣化粧にしても、このスコットランドの大地から湧き出してきたようなものにしたいと考えていた。とても自然発生的だった。この映画の映像は、何よりもスコットランドの土地と風景に導かれたものなんだ。
それを楽しみましたか?
それはもう、本当に気に入ったよ。でもとても大変だった。厳しく、容赦なく、恐ろしい自然。それと取り組み、ぴったりの時期を見計らいながら、残酷な気候の中で、かなり短い期間に撮影した。本当に親密なセリフを話すシーンを、信じられないほどの強風の中で撮影したこともある。一介のオーストラリア人がイギリスに突然やってきて、社会派リアリズムの映画を監督する。しかも現在世界最高の俳優二人と一緒に、最も有名な戯曲の監督を務めるなんて、本当に気後れする。でも僕はいつも自分を怯えさせるようなことをやり遂げてきた。それは『スノータウン』でも変わらない僕の姿勢なんだ。
(オフィシャル素材提供)
![]()
関連記事
・日本版“マクベス夫妻”お披露目イベント




