『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』初日舞台挨拶
2022-03-21 更新
伊藤雄馬(出演の言語学者)、金子 遊監督
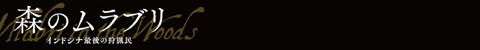
 ©幻視社
©幻視社配給:オムロ 幻視社
シアター・イメージフォーラムにて公開中 全国順次公開
![]()
持続可能な生活を追った映像人類学のドキュメンタリー映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』。本作は、6ヵ国語を自由に話し、文字のないムラブリ語の語彙を収集する、言語学者・伊藤雄馬とともに足かけ2年、ムラブリ族を追ったドキュメンタリー。初日舞台挨拶には、本作出演の言語学者・伊藤雄馬と、本作監督の金子 遊が登壇し、撮影の裏話やムラブリ族から学べるサステナブルな生き方などについて語った。
舞台挨拶の冒頭、金子監督が、伊藤氏との出会いについて、「アピチャッポンの『トロピカル・マラディ』や『ブンミおじさんの森』といった映画を見た影響で、タイのバンコクや海側のリゾート地ばかりではなく、タイの北部や山地に興味が行くようになった。僕が2017年の2月と3月にタイとカンボジアの山あいのゾミアと呼ばれる地域の少数民族の文化と、そこで撮られた映画や映像の研究で回っていた頃に、以前オーストリアの民族学者ベルナツィークの『黄色い葉の精霊』で読んだムラブリを探しに行ったんです。タイのナーン県の劇中でムラブリの一番大きなコミュニティとして出てくるフワイヤク村まで行って、現地のガイドの方を雇って、かなり山奥まで連れて行ってもらいました。そこで映像を撮ったりいろいろなムラブリの人にインタビューをしていたら、そこに住み込みで研究している伊藤さんにばったり出会いました」と説明。
伊藤氏も、「僕も驚いたんです。日本の方が来ることはないので。『誰かが来ている』というので、タイ人かなと思ったら日本人で」と当時の驚きを話した。
金子監督は、その出会いから本作が生まれたいきさつについて、「会った初日に(3ヵ所に分かれている)ムラブリの人たちがお互い“人食い”という伝説があって嫌い合っていて、100年以上お互い会っていないということと、タイ、ラオスにABCグループがいて、伊藤さんが長老のパーさんをなんとかラオス側に連れて行って、ラオス側のムラブリに会ってもらいたいという話をして、『それは映画になりますね』とやる気になって、2018年の2月と3月で数週間かけて今日観ていただいた映像のほとんどを撮りました」と話した。
伊藤氏は、ムラブリ語の研究を始めた理由は、「彼らの言葉の響きに惹かれ、ムラブリ語の研究を始めました。大学の時にフィールドに出て(現地に行って)調査するような研究をしたいと思っていたんですが、場所が決まらなかったんです。ある時人類学の授業で見た『ウルルン滞在記』に(既に定住を始めていたタイ側の)ムラブリが出ていて、ムラブリ語の響きがいいなと思った」と、『ウルルン滞在記』が決め手になったという驚きの事実を話した。
ムラブリ語の研究を始めてからの発見について、「方言もありました。現在確認されている全ての方言が、本作で紹介している3つの方言です。彼らは動いて生活するため、土地の名前に縛られないので、ABCと呼んでいます。例えば僕は島根県の石見出身で、石見方言の母語話者ですけれど、彼らは『どこどこ地方』というのがないので、ABCと呼ぶしかないです。方言は少なくとも3つはあります。それぞれ違うというのも、日本語の方言のようなイントネーションやアクセントの違いでなく、『鼻』などの語彙が全然違うんです。なぜかといったら、お互いを『あいつらは人を喰う』とか、『凶暴だ』と言って、(格好は一緒なので)区別するために言葉を目印にして自分たちの集団を分けていたのではないかと僕は考えています」と解説。
今回世界初となったいまだノマド生活を送るラオス側のムラブリ族の撮影について、金子監督は「僕たちは観光局とお話して、さらに地元の有力者に会って許可をもらって撮れることになった」と説明。
ラオス側の野営地については、金子は「3時間くらいで着くよと言われたけれど、5時間くらいかかった。道じゃないところを歩き、不安だったけれど、たどり着くことができた」と話し、伊藤氏は、「ベルナツィークの『黄色い葉の精霊』の中で、ムラブリの『黄色い葉の精霊』という呼び名の元になった、葉っぱが黄色くなった風除けの家の様子そのままだったので、『うぉー! 本のまんまじゃん』とすごくびっくりしました。本の中でしか読んだことがなくて、(定住を始めている)タイ側ではもう使っているものではない。こういう経験は研究者冥利に尽きます」と感無量の様子だった。
ラスト・シーンについては、金子監督が、「僕たちがお願いして歩いて、『会いに行こうよ』とタイ側のお互い会っていなかったグループ同士を引きあわせるという形になっているけれど、彼らの内側からきたものもあります。それがなかったら実現していません」と話すと、伊藤は「僕がタイの二つのグループを行ったり来たりしていると、『危ない。大丈夫なの?』と言われるんですが、『大丈夫だよ』と帰ってくると、徐々に『会ってもいいのかな?』と思ったみたいで、本作の撮影のタイミングで、『ちょっと会ってみない?』と言ってみた」とこれまでの経緯を話した。
二つのグループの接触の撮影を終え、金子は「僕らはきっかけにすぎなくて、おそらく20~30年かけて現在定住しているフワイヤク村が作られている間に、パーさんたちが森の中にいる人たちに会いに行って、オルグじゃないけれど、『同じ民族だから一緒に住もうよ』ということを繰り返しやってきたんだろうなという気がしました」と感触を話すと、伊藤氏も「100年以上ぶりに会うからどうかなと思っていたんですけれど、こういう場面が今までいっぱいあったんだろうな、くっつくこともあれば、離れることもあると気づかされました。ムラブリは400~500人しかないですが、これからもムラブリはくっついたり離れたりがあるんだろうなと改めて感じました」と、本作を撮影したから分かったことを話した。
伊藤氏は、ムラブリの村から持ってきたグッズを幾つか披露する場面も。写真は、ムラブリの人と一緒に森に入った時に「お前、迷子になるから、迷子になったらこれ吹けよ」と頂いたという笛。

最後に監督は、「ウクライナで戦争が起きていますし、先日も巨大地震があり、温暖化の影響で気象の変動があって、自分たちもいつ家がなくなって、避難民になるかも分からない時代になってきましたが、ムラブリの人たちの生活を見ると、川があって水が得られて、イモを掘って、魚位が取れれば、どこでも暮らせるし、彼らが羨ましいと思いました。“狩猟採集民”というと、忙しい大変な人たちかなと思っていたら、ずっとゴロゴロしています。働くのは薪を取ってきて火を絶やさないのと、食べ物を作る時位なので、1日1~2時間くらい。僕らはいつも『電車を乗り過ごしてはいけない』、『学校や仕事に間に合わなくてはいけない』というプレシャーがありますけど、こういうオルタナティブな生活が森の中にあるんだと考えるだけで、ふっと深呼吸ができるというか、『いつでもこの生活になれるんなら、今を生きていける』という気がする」と心境を吐露。
伊藤氏も、「ラオス側のムラブリを見て、『お前、物持ちすぎだぞ。ごちゃごちゃ生きていないか』と言われ続けている気がして、僕自身も変わってきました。例えば今ふんどしを履いて、雪駄を履いたり、物質文化からちょっと距離を置くような感性が生まれました。大学教員を辞めて、独立研究者になりました。大学教員の時は、研究をしたくて大学教員になったのに、忙しくて研究ができなかった。なので、自分で自給自足みたいな生活をして、余った時間で自分がしたい研究をするほうが僕はずっとシンプルだなと思って、自活研究者として自分で家を作ったり、農業を始めています」とムラブリの自身への影響を話した。
(オフィシャル素材提供)
![]()
関連記事
・金子 遊監督 オフィシャル・インタビュー



